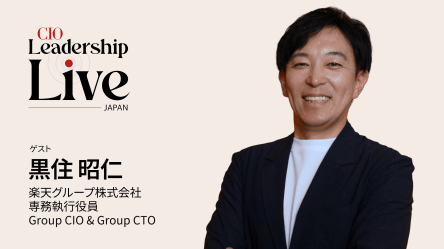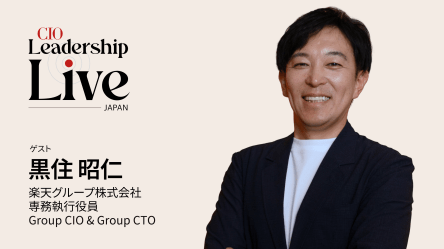システムやアプリケーション開発業務を海外の専門企業に委託する「オフショア開発」は、今や日本のIT企業の約6割が導入する一般的な開発手法として定着している。かつてその主目的は、国内に比べて安価な人件費を背景とした徹底的なコスト削減にあった。しかし、近年その様相は劇的に変化している。深刻化する国内のIT人材不足を背景に、単なるコスト削減策としてではなく、「優秀な人材リソースの確保」や「AI・データ分析といった先端技術領域での高品質な開発」、さらには「グローバルな研究開発(R&D)拠点」としての活用といった、より戦略的で高度なニーズが急増しているのだ。本稿では、日本企業を取り巻くオフショア開発の変遷を、委託先地域のトレンド、求められる技術領域、変化する評価軸、そして激動する外部環境といった多角的な視点から紐解き、その未来像を展望する。

変遷するオフショア開発の地図
日本企業のオフショア開発の歴史は、委託先地域の変遷の歴史でもある。かつての「中国一択」の時代から、現在はより多様で複雑な選択が求められる多極化の時代へと移行している。
中国一強時代の終焉と東南アジアの台頭
日本におけるオフショア開発は1980年代に始まり、その黎明期を支えたのは地理的にも文化的にも近い中国であった。多くの中国人が日本語を習得し、日本の開発案件を請け負うことで、オフショア開発の礎が築かれた。しかし、その後の中国経済の急成長に伴う人件費の高騰、そして米中対立や台湾問題を背景とした政治的リスク、いわゆる「チャイナリスク」が顕在化するにつれ、日本企業はオフショア先の分散化を強く意識するようになった。特に近年、中国当局による反スパイ法の改正など情報統制の強化は、外資系企業にとって予測不能なリスクとなり、欧米企業を中心に「脱中国」の動きが加速している。日本企業も例外ではなく、サプライチェーン再編の一環として、開発拠点を東南アジアへ移転・分散させる動きが活発化している。現在の中国は、優秀な技術者層を抱える一方で人件費単価も上昇しており、純粋なコスト削減を目的とするオフショア先としては、その魅力が相対的に低下しているのが実情である。
ベトナムの不動の地位と、英語圏の追い上げ
中国に代わるオフショア先として、今や不動の地位を築いているのがベトナムだ。2023年の調査では、日本企業が相談する委託先国のうち約半数がベトナムであり、3年連続で圧倒的なシェアを維持している。その人気の背景には、国策として毎年5万人規模のIT人材が安定的に輩出される供給力、10年以上にわたる日本向け開発で蓄積された豊富なノウハウと高い信頼性、そしてAIなどの先端技術に精通した高スキル人材の存在がある。日本語や英語に対応可能な技術者も多く、近年の単価上昇を加味してもなお、品質とコストのバランスに優れた選択肢として高く評価されている。
一方で、新たな潮流としてフィリピンやインドといった英語圏の国々のシェアが微増している点も見逃せない。これらの国々は、公用語やビジネス言語として英語が広く通用するため、プロジェクトを英語で直接推進したいと考える企業からの支持を集めている。国内の人口減少と経済停滞を背景に、日本企業がグローバル市場を視野に入れたサービス開発を志向する中で、社内公用語を英語に切り替えてでも海外の優秀な人材を活用しようという動きが生まれつつある。翻訳ツールの進化も後押しとなり、従来の日本語ブリッジSEを介するスタイルではなく、日本側の担当者が直接英語で現地の開発メンバーとコミュニケーションを取るケースが増加しており、これが英語人材が豊富なフィリピンやインドの人気上昇につながっていると考えられる。
このほか、ミャンマーは2021年のクーデターによる政情不安が、中国は前述の地政学リスクがそれぞれカントリーリスクとして強く懸念され、人気が伸び悩んでいる。また、「ポスト・ベトナム」候補として、人件費の安さで注目されるバングラデシュや、IT人材の質が高いウクライナ・東欧諸国も存在するが、技術水準や地政学リスクの観点から、日本企業の進出はまだ限定的である。オフショア先の選定は、言語、文化、コスト、リスクを総合的に勘案する、複雑な戦略的判断へと進化しているのだ。
目的と評価軸のパラダイムシフト
委託先が変化すると同時に、オフショア開発に求めるもの、すなわち企業側の目的意識と評価軸も大きく転換している。もはや「安かろう悪かろう」は許容されず、より本質的な価値が問われる時代になった。
「コスト削減」から「高度IT人材の確保」へ
長らくオフショア開発の最大の動機はコスト削減であったが、2023年の調査でついにその首位の座を「人材リソース確保」が奪取した。これは、オフショア開発の本質的な目的が「安さ」から「人材」へと明確にシフトしたことを示す象徴的な出来事である。この背景には二つの大きな要因がある。一つは、年々深刻化する日本国内のIT人材不足だ。経済産業省の試算では2030年に約80万人もの人材が不足すると予測されており、国内だけで開発体制を維持することが極めて困難になっている。もう一つは、2022年以降の急激な円安だ。歴史的な円安は海外への委託費用を相対的に押し上げ、コスト削減効果を大きく減退させた。
この変化は企業規模によって異なる反応を引き起こしている。特に中小企業はコストメリットの減少に敏感であり、一部ではオフショアから国内のニアショア開発や内製化へ回帰する動きも見られる。一方で、大企業にとっては国内の人材獲得競争が熾烈を極める中、円安というコスト増を吸収してでも海外の優秀なIT人材を確保する必要性が勝っており、むしろオフショア活用を拡大する傾向にある。全体として見れば、「安いから海外に外注する」という発想から、「国内に人がいないから海外に頼らざるを得ない」という、より切実な動機へと軸足が移っていることは間違いない。
品質とコミュニケーション、そしてセキュリティという新たな砦
コスト一辺倒だった評価軸は多様化し、近年では開発の品質、円滑なコミュニケーション、そして体制の信頼性がより強く重視されるようになった。オフショア開発で直面する課題として「コミュニケーション能力」と「品質管理」が常に上位に挙げられることからも、これらの重要性は明らかだ。日本語の細かなニュアンスが伝わらなかったり、品質管理体制に不安があったりする委託先では、たとえ安価であってもプロジェクトは失敗に終わる可能性が高い。そのため、多少コストが高くとも、過去の実績が豊富で、高い技術力を持ち、コミュニケーション対応が優れたパートナーを選ぶ企業が増えている。
さらに、サイバーセキュリティへの関心も急速に高まっている。開発中のソースコードや機密データの情報漏洩リスクは、企業の存続を揺るがしかねない重大な問題だ。2021年に発生した大手電子部品メーカーの情報流出事件は、委託先の海外現地エンジニアがデータを不正に持ち出したことが原因であり、オフショア開発における情報管理の脆弱性を浮き彫りにした。特に中国では「国家情報法」により、企業が保有する情報が当局の命令一つで開示されうるリスクが指摘されており、セキュリティ意識の違いは看過できない。こうした背景から、日本企業は委託先を選定する際に、各国の法制度やセキュリティ文化までを精査し、通信の暗号化、VPNの利用、ゼロトラストアーキテクチャの採用など、より強固な対策を講じるようになっている。コスト削減とセキュリティ強化という、時に相反する要求を両立させるという難題に、各社が真剣に取り組んでいるのが現状である。
技術領域の拡大と深化
オフショア開発で委託される業務内容も、単純なコーディングやテストから、より高度で専門的な領域へと拡大している。これは、海外人材のスキル向上と、日本企業側のニーズの変化が合致した結果と言える。
AI・クラウド開発というフロンティアへ
かつてのオフショア開発は、Webサイト制作や業務システムの保守・運用といった比較的定型的な業務が中心だった。しかし近年、AI、データ分析、IoT、Web3といった先端技術領域の開発案件が急増している。特にベトナムでは、これらの先端分野で豊富な経験を持つエンジニアが多く、日本企業にとって魅力的な開発パートナーとなっている。また、世界最高峰の工科大学を擁するインドも、データサイエンティストやAIエンジニアの一大供給地であるが、需要過多により人件費が高騰しており、効率的なラボ型契約などを活用しなければコストメリットを出しにくい状況だ。
一方で、クラウドコンピューティングの普及もオフショア開発の風景を一変させた。AWSやAzureといったクラウド基盤や、多彩なプロジェクト管理ツールが発達したことで、物理的な距離を越えて効率的にプロジェクトを管理・共有できるようになった。これにより、スタートアップから大企業まで、あらゆる規模の企業がオフショア開発に取り組みやすくなった。また、DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速に伴い、既存のレガシーシステムからクラウド環境への移行(マイグレーション)や、クラウド基盤そのものの構築・運用といった新たなニーズも生まれている。
レガシーシステム保守という新たな活路
技術領域の変化は、先端分野への拡大だけではない。むしろその逆、日本国内で技術者の高齢化と後継者不足が深刻なレガシーシステム(特にCOBOLなど)の保守・運用においても、オフショア活用が新たな活路として注目されている。大規模な金融機関や行政機関で長年稼働してきたCOBOLシステムは、熟練エンジニアの引退が進む一方で若手技術者が育たず、運用保守コストの高騰と技術的負債の増大が経営課題となっている。この問題を解決するため、ベトナムのホーチミン市にCOBOL開発を専門とするオフショア拠点を設立し、現地の大学と連携して若手人材を育成することで、日本のレガシーシステムを永続的に維持しようという先進的な取り組みも始まっている。このように、最先端のAI開発から旧来システムの延命まで、日本企業が海外に求める技術の幅はかつてなく広がっている。
外部環境がもたらした激動と企業の対応
2020年以降、世界はパンデミック、急激な為替変動、そして地政学リスクの高まりという未曾有の激動に見舞われた。これらの外部環境の変化は、オフショア開発のあり方にも profound な影響を与えている。
パンデミックと円安が変えたコスト構造
新型コロナウイルスの感染拡大は、皮肉にもオフショア開発を加速させる一因となった。感染拡大初期こそ国際的な移動制限でプロジェクトの立ち上げが停滞したが、その後のリモートワークの急速な普及は、業務の非対面化を常態化させた。これにより地理的な距離のハンデが大幅に縮小し、「場所を問わず開発できる」という環境が整備された。かつて必要だった海外出張や駐在員派遣なしにプロジェクトを推進できることが証明され、多くの企業がリモート前提での海外人材活用へと舵を切った。
一方で、前述の通り、2022年からの歴史的な円安はオフショアのコスト構造を直撃した。海外委託費用が円建てで大幅に増加し、特にコストに敏感な中小企業のオフショア離れを促す結果となった。東南アジア各国の賃金上昇も相まって、かつてのような圧倒的なコスト差はもはや存在しない。しかし、国内の構造的な人材不足という課題は円安以上に深刻であり、特に大企業は為替変動リスクを織り込み済みで、開発リソース確保のために海外活用を継続・拡大している。
地政学リスクと「脱中国」という不可逆な流れ
米中対立の激化やロシアによるウクライナ侵攻など、世界的な地政学リスクの高まりは、オフショア先の選定において「安定性」という評価軸の重要度を格段に引き上げた。ミャンマーの政情不安や、ウクライナおよびその周辺国での開発プロジェクトの中断は、政治リスクが事業継続に直接的な脅威となることを企業に再認識させた。
中でも最も大きな影響を及ぼしているのが、中国をめぐるリスクである。米国の先端技術分野における対中規制強化や、中国国内での予見不能な事業リスクを背景に、欧米企業のみならず日本企業の間でも、生産・開発拠点を中国から東南アジアや国内へ移転・再編する動きが加速している。オフショア開発においても、政治的リスクを回避するためにベトナムなどへシフトする流れは明確であり、「コストが安くても政治リスクの高い国は避ける」という傾向は、今後ますます強まるだろう。
企業規模で見るオフショア戦略の多様化
オフショア開発との向き合い方は、企業の規模によっても大きく異なる。それぞれの置かれた状況や経営体力に応じて、多様な戦略が採られている。
戦略的拠点として活用する大企業
従業員5000名を超えるような大企業では、慢性的なエンジニア不足への対策として、オフショア開発を戦略的に拡大する動きが顕著だ。NTTデータや富士通といったIT大手は、インドやベトナムに自社の開発拠点や子会社を設立し、グローバルな開発体制を構築している。また、Sansanがフィリピンに、LINEヤフーやマネーフォワードがベトナムに自社開発拠点を置くように、Webサービス系企業でも、単なる業務委託ではなく、自社プロダクト開発の中核を海外に置く例が増えている。大企業にとってオフショアは、コスト削減策というよりも、海外市場展開、24時間開発体制の構築、そしてグローバルな優秀人材の獲得といった、より高度な経営戦略の一環と位置づけられている。
リソース補完を急ぐ中堅企業
国内のシステムインテグレーター(SIer)やソフトウェアハウスなどの中堅IT企業も、オフショア活用を本格化させている。深刻なエンジニア不足と旺盛なIT需要の板挟みとなり、自社内や国内パートナーだけでは開発リソースを賄いきれなくなっているからだ。「受注した案件に適したスキルを持つエンジニアが社内にいない」「開発要員が足りない」といった課題を解決するため、ベトナムなどの海外パートナー企業と協働チームを組成する動きが活発化している。自前で海外拠点を持つよりも、信頼できる現地企業との提携を選択し、要件定義や基本設計は日本側が、詳細設計以降の実装・テストは海外側が担うといった分業体制を敷くことで、不足するリソースを効率的に補完している。
国内回帰も視野に入れる中小企業
一方、従業員規模の小さい中小企業では、オフショア開発に対して慎重、あるいは消極的な姿勢が強まっている。円安によるコストメリットの低下に加え、小規模な組織では海外委託に伴う管理負荷やコミュニケーションの障壁が相対的に大きくなるためだ。限られた人員の中で、時差の調整や品質チェックに過大な工数を割くことは本末転倒になりかねない。「安さにつられて導入したが、うまくいかなかった」という経験から、国内の開発会社やフリーランスへと委託先を切り替える、いわゆる「国内回帰」の動きも散見される。中小企業は、オフショアのメリットとデメリットをよりシビアに天秤にかけ、自社にとって最適な開発体制を慎重に模索するフェーズに入っていると言えるだろう。
オフショアのその先へ – ニアショアと最適化の時代
オフショア開発が一般化し、その功罪が明らかになる中で、新たな代替策や、より洗練された活用法が模索されている。それは、単に海外に委託するという一辺倒な考え方からの脱却を意味する。
ニアショア開発という国内の選択肢
オフショアの代替策として近年急速に注目を集めているのが「ニアショア開発」だ。これは、開発業務を東京などの都市部から、沖縄、北海道、九州といった地方都市の企業に委託する手法である。海外ではなく国内で完結するため、言語や文化、商習慣の違いがなく、コミュニケーションが極めて円滑に進められるという大きなメリットがある。時差もなく、緊急時の対応や対面での打ち合わせも容易だ。地方は都市部に比べて人件費やオフィス賃料が安価なため、一定のコスト削減効果も見込める。コロナ禍でリモートワークが定着し、遠隔地との協業に対する心理的障壁が下がったことも、ニアショアの普及を力強く後押しした。コスト削減と人材確保、そして円滑なコミュニケーションを両立できる選択肢として、特に中小企業を中心に国内回帰の有力な受け皿となっている。
日本企業の未来を拓くグローバルリソース戦略
日本企業によるオフショア開発は、大きな転換点を経て、新たなステージへと進化を遂げようとしている。委託先は多極化し、目的はコスト削減から高度人材の確保へ、技術領域は最先端分野へと広がった。もはや、闇雲に海外へ委託すれば成功する時代は終わった。これからは、自社の状況やプロジェクトの特性に応じて、オンショア(国内)、ニアショア、そしてオフショアを最適に組み合わせる「ベストショア」の考え方が主流となるだろう。例えば、顧客との対話が重要な要件定義は国内のニアショアで、実装やテストはコストを抑えられるオフショアで、といったハイブリッド型の活用が一層進むはずだ。
深刻なIT人材不足という日本の構造的課題を乗り越えるためには、海外の優秀なエンジニアの活用が不可欠であることに疑いの余地はない。多くの企業が今後もオフショア開発を拡大していくと予測されている。しかし、その道のりは平坦ではない。短期的な成果を求めるのではなく、異文化コミュニケーションの壁や品質管理の課題に粘り強く向き合い、長期的な視点でパートナーシップを構築していく覚悟が求められる。グローバルな視野で最適なリソースを確保し、品質、セキュリティ、コストの絶妙なバランスを追求する。その絶え間ない最適化の先にこそ、日本企業の新たな競争力と未来が拓かれるのである。