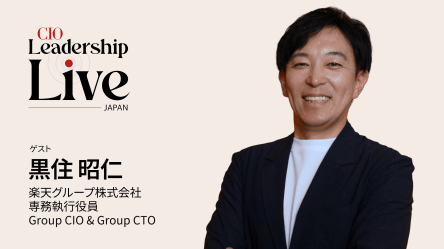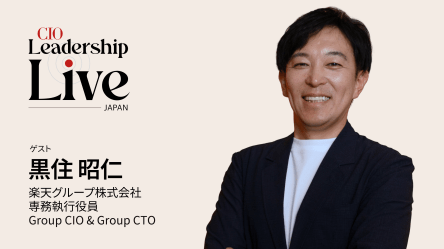情プラ法は、インターネット上の権利侵害への対応を「速く」「わかりやすく」するために、一定規模のプラットフォームに手続上の義務を課す法律です。本稿ではこの法律を詳しく解説します。

1. 背景と目的
2001年に制定されたプロバイダ責任制限法は、プロバイダの損害賠償責任の限定と発信者情報開示を定めるものでした。その後、SNSやUGCの拡大により、名誉毀損やプライバシー侵害などの情報が短時間に広がる事例が増え、被害者からは「窓口が見つけにくい」「対応が遅い」「結果や理由が届かない」といった不満が積み上がりました。一方で、規約に基づく自主的削除の透明性が不足し、表現の自由に関する懸念も指摘されてきました。こうした状況を踏まえ、手続きを整え、判断と説明を可視化するために導入されたのが情プラ法です。削除すべき内容を行政が決める仕組みではなく、各社が自らの基準に従って判断し、そのプロセスと結果を明らかにする設計になっています。
2. 法の位置づけと沿革
情プラ法は、プロバイダ責任制限法の改正により成立し、法律名が改められました。2021年改正では、発信者情報開示命令の手続が創設され、被害者が一つの枠組みで開示を求められるようになりました。今回の改正では、一定規模のプラットフォームに対して、権利侵害情報への対応の迅速化と、削除運用の透明化に関する義務が新設されています。罰則も整備され、勧告・命令に従わない場合には刑事罰の対象となります。
3. 指定の考え方(誰が対象か)
義務の主体は、総務大臣が指定する「大規模特定電気通信役務提供者」です。対象となるのは、ユーザーが情報を発信して相互にやり取りするサービスで、発信者数や投稿数が一定規模を超えるものです。登録型サービスでは平均月間発信者数、非登録型サービスでは平均月間延べ発信者数を基準に判断されます。海外ユーザーは原則として算定から除外されます。チャット機能が付随するにとどまるオンラインゲームのように、権利侵害が生じにくい用途は対象外と整理されています。基準に到達していなくても、成長が見込まれるサービスは、早い段階から受付と判断の枠組みを整えておくのが安全です。
4. 求められる義務の全体像
情プラ法の義務は、大きく「対応の迅速化」と「運用の透明化」に分かれます。対応の迅速化では、オンラインで利用しやすい申出窓口の常設、申出の受付から一定期間内の調査と判断、結果と理由の通知、専門的判断に対応できる人員体制の整備が求められます。透明化では、削除の対象となる情報をできる限り具体的に定めた基準の公表、削除時の発信者への通知、そして年に一度の実施状況の公表が求められます。これらは、削除の可否そのものを国が指示するのではなく、手続きを整え、説明可能性を高めることに主眼があります。
5. 日々の運用の流れ(受付から通知まで)
実務では、被害申出の受付時点で期限管理を開始し、必要な情報が揃っているかを確認します。不足があれば速やかに追加情報を求めます。同一の投稿に関する複数の申出は整理し、判断をそろえるようにします。事実関係の確認を行い、緊急の危険がある場合は暫定的な対応を検討します。専門的な判断が必要な案件は、担当者から専門員へ引き継ぎ、先例や社内ガイドを参照しながら結論を出します。結論に至ったら、削除する場合もしない場合も、申出者に結果と理由を伝えます。発信者への通知が必要なときは、その手続も併せて行い、記録を残します。これら一連の流れは、原則として短期間で完結させることが求められます。
6. 侵害情報調査専門員の配置
難易度の高い案件に適切に対応するため、各社は「侵害情報調査専門員」を置きます。社内の法務や信頼・安全の担当者に加え、必要に応じて外部の専門家と連携します。複数の役務を運営する企業では、サービスごとの特性に合わせた判断基準を整備し、教育とレビューの機会を定期的に設けると、判断のばらつきを抑えられます。外部の専門家に依頼する場合は、弁護士法との関係に注意し、具体的な事案に応じた適切な関与の範囲を設計します。
7. 削除基準の設計と公開
削除の対象となる情報の種類は、利用者にとって理解しやすい言葉で示します。典型的な違法情報に加え、境界事例についても考え方を示すと、誤解が減ります。公開文書は簡潔に保ちつつ、社内には、事例と評価観点、エスカレーションの条件、緊急時の対応方針を含む詳細な手引を整備します。公開する前に、法務、信頼・安全、広報、プロダクトで確認し、規約や法律との整合を確かめます。改訂した場合は、変更点と理由を社内で共有し、必要に応じて外部にもわかる形で説明します。
8. 実施状況の公表とデータ基盤
年に一度の公表は、日々の運用データが整っていれば負担を減らせます。受付件数、判断までの日数、削除・非削除の件数、主な非削除理由、発信者への通知の実施状況などを、サービス別や期間別に集計できるようにしておきます。個人情報や機密情報に配慮しつつ、推移や改善計画も併せて示すと、外部からの理解が得やすくなります。内部では、期限の遅延や特定の類型の偏りに早めに気づけるよう、モニタリングの仕組みを用意すると効果的です。
9. 罰則とコンプライアンス
指定を受けた事業者が義務を履行せず、勧告や命令にも従わない場合、刑事罰の対象になります。指定や報告、届出に関する違反には罰金や過料の規定があり、法人に対する両罰規定も設けられています。法令本文と省令・ガイドラインを突き合わせ、窓口の表示、体制、記録、通知の文面まで、社内規程として文書化しておくことが重要です。
一体設計が重要
情プラ法は、削除の中身を国が決める仕組みではありません。各社が基準を作り、申出に迅速に応答し、結果と理由を伝え、運用の全体像を公表することが求められます。まずは、自社のサービスが指定対象になり得るかを確認し、オンライン窓口、期限管理、専門員の配置、記録と公表の手順を一体で設計するのが望ましいでしょう。これらを先回りで整えることは、法令遵守だけでなく、利用者の信頼と運営コストの安定にもつながります。